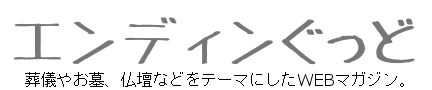過去帳とは
日本では多くの家庭で仏式の葬儀が執り行われます。
そのため、葬儀の後には自宅に仏壇を設置することが多いです。
ただ、仏教の儀式では使う道具も多く用意するのに何が必要かわからなくなってしまうこともあります。
そういったものの一つが過去帳です。
過去帳というのは仏式の儀式で使われている道具の一つで、代々の亡くなった方々の戒名や俗名、没年月日、享年といった情報を書き残していきます。
浄土真宗ではほかの宗派とちがい位牌には魂が宿ると考えられていないので、位牌を祀らずに過去帳を仏壇に飾るのが一般的です。
江戸時代には寺受け制度があったため、誰もが寺院の檀家になることが義務付けられていました。
その際に、戸籍の役割を果たす台帳として檀家それぞれの過去帳を作成していったことが現在にも残っていてこのような過去帳があるのです。
過去帳があればその家の家系図をたどっていくことができます。
そういった観点から最近では個人情報保護のためにも過去帳を作成をしていても仏壇には置かずに人目のつかないところに保管をしているというところも多いです。
過去帳の保管法
過去帳は各家庭の仏壇に置かれています。
ただ、大切なものでもあるので仏壇にある引き出しにしまうことが一般的です。
月命日や法事になると飾るようにします。
中身についても日付があるものとないものとがあり様々です。
日付があるものは1日から31日までのページがあり亡くなった日のページにその人の情報が書かれています。
これは毎日めくることで故人の命日を確認することができ、供養ができるのです。
それに対して日付がないものは没年月日順に書いていくために年表形式になっています。
そのため記録簿としての役割を果たしており、寺院で使われているタイプはほとんどがこのタイプです。
過去帳と同じような内容が書かれているものに本位牌があります。
位牌にも過去帳のように故人の名前や没年月日、享年といったものが書かれているのですが、書かれている内容は同じでもその特性は違っているものです。
本位牌はその人の魂が込められているものであり、死後はその人の分身のような扱いをしています。
それに対して過去帳は家系図としての意味合いが強いです。
こういった違いから位牌は常に目に付くところに出されていますが、過去帳は人目につかないところに置かれています。
また、位牌は数が増えると法要の節目にお寺で処分をしたりまとめたりすることが多いです。
それに対して過去帳は永続的に使い続けていきます。
位牌は作成を依頼しますが、過去帳は誰が記録を記載してもいいという点も違う点です。
過去帳はいろいろな種類があり、形も素材も種類があります。