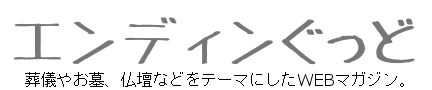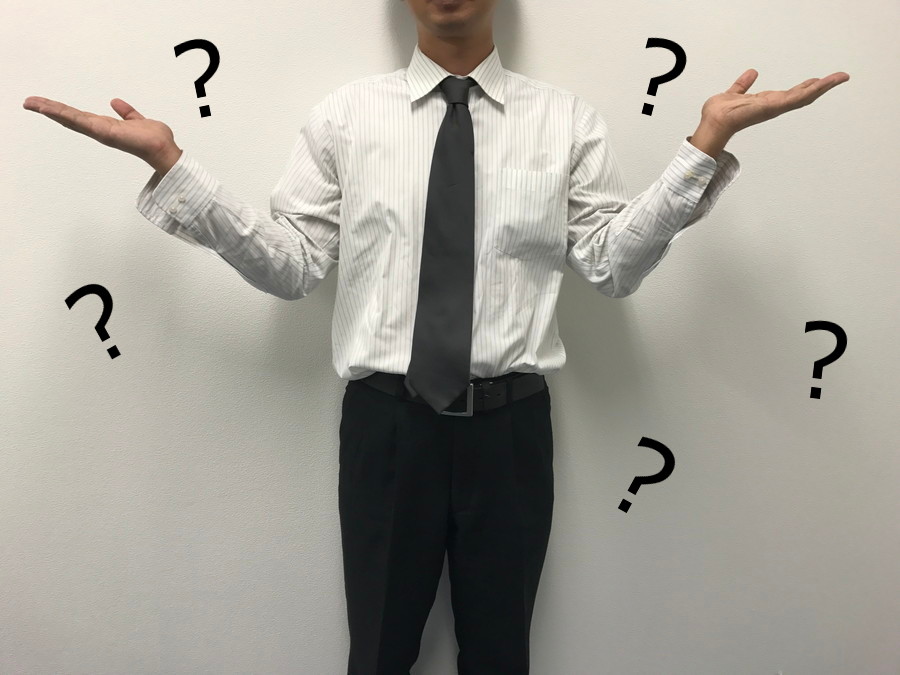社葬は会社で行う葬儀ではない!
社葬という言葉だけは耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、社葬は、会社で行われる葬儀、というわけではありません。
会社の創業者や重役など、企業にとって重要人物を始め、社員が仕事中に殉職をしたなどの際に、会社側が執り行う葬儀のことをさします。
会社で行われることもありますが、基本的には葬儀会場を利用し、一通り式の手順を全て踏んで、従業員全員で、故人をともらうようになるでしょう。
企業が執り行う式ではありますが、基本的には、社長秘書など、重役に近しい方を始め、部長などの役付き、新入社員など問わずに、葬儀の受付などを任命されるでしょう。
葬儀会場スタッフに任せるのではなく、従業員で賄うことが出来る部分は、積極的に社員を利用するのも、社葬の一つの特徴であると言えます。
社葬の喪主は誰になる?
社葬の場合の喪主は、個人葬の場合と変わらずに、遺族が喪主となります。
ただし、お葬式の費用負担や運営が、故人の勤めていた企業が行うことが、社葬の大きな特徴といえるでしょう。
企業の経費でお葬式が執り行われますので、規模が多少大きくなる傾向があります。
従業員の参列が基本ではありますが、少人数からでも社葬は実施が可能ですので、仕事の関係で急きょスケジュールを付けるのが難しいというタイミングの場合は、小規模で行われることも多いでしょう。
参列者は社葬の場合、会社関係者やクライアントのみになりますので、別途、家族葬や個人葬を行うというご遺族が少なくありません。
社葬の費用は会社持ち
社葬をとり行う際の費用は企業持ちとなりますが、何でも葬儀費用として賄われるわけではありません。
費用として認められる種類が限られていますので、社葬を行う際には注意が必要でしょう。
まずは、不法通知の新聞広告料や、案内状の作成、発送費用など、式開始前の通知段階があげられます。
次に、祭壇料や葬儀場の使用料、お坊さんなどへのお礼料や粗品、警備員の配置など、葬儀に関しての費用です。
そして、手伝った社員の慰労会食事代、写真ビデオ撮影料なども、企業負担として認められているでしょう。
葬儀と関係ないこの他の費用は、経費として認められていませんので、注意が必要です。
香典返しや戒名料などは、原則として社葬の経費には含まれず、ご遺族の負担となりますので、十分注意をしましょう。
こちらを経費で賄ってしまうと、贈与税の対象となってしまいますので、反対に遺族に負担がかかります。
このように社葬は規模を大きく行うことが出来ますが、その分何かと制限があることや、注意をしないといけないこともありますので、とり行う際には色々と確認を取る必要があるでしょう。