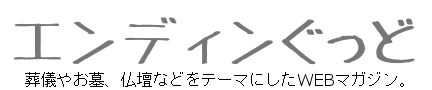四十九日法要は大切な法要
亡くなった人は死後49日で仏様の元へと向かうとされています。
そのため49日目に四十九日法要という大きな法要をするのです。
法要を行うためには自宅で行うのか、セレモニーホールや菩提寺を利用するのか、といったことを決めていく必要があります。
それ以外にも補用を行うためには準備をしなければなりません。
きちんと故人を仏様の元へ送るためにも正しい法要の方補を理解しておきましょう。
四十九日法要を行うための準備
四十九日法要は仏教でとても大切な法要です。
極楽浄土に故人が行くために遺族も7日ごとに祈るための法要をします。
それが初七日から始まり7回目の法要が四十九日法要となるのです。
四十九日法要が判断が下される法要であり、規模も大きくなります。
そのために準備がいろいろと必要です。
葬儀が終わったらできるだけ早く日時と会場の手配をします。
日時を決める際にはできるだけ四十九日にあたる日にしますが、平日の場合には四十九日の手前にある土日を選ぶのが一般的です。
四十九日を過ぎてから行うことになると故人が待つことになってしまいますから失礼の内容に前倒して行います。
日にちについては必ず四十九日にするよりは多くの人が集まりやすいように土日を選ぶことの方が優先度としては大切です。
また、身内の中でスケジュールの問題で集まるのが難しいという場合には直近の土日ではなくもう少し前の土日を選ぶというケースもあります。
大体のスケジュールが決まったら僧侶への連絡と場所の決定が必要です。
自宅でなく菩提寺やセレモニーホールを利用する場合にはそれらの施設の都合がありますし、僧侶の予定によっても日程が変わる可能性があります。
また、お墓の準備もできた場合には四十九日法要の後に納骨も行いますから納骨の法要も併せて依頼するようにしましょう。
四十九日法要の日程が完全に決まったら再度連絡をして日程のお知らせをします。
昔は案内状を用意して送っていましたが、親族のみの場合には電話での連絡でも問題ないです。
二週間前までに準備すること
四十九日法要の予定が決まったらその2週間前までに位牌の準備が必要になります。
白木の位牌は四十九日法要以降黒い本位牌に代わるため、その手配をしなければならないのです。
戒名などの文字入れがあるので1週間から2週間ほどかかります。
また、仏壇を購入する際も購入してすぐに自宅に届くとは限りません。
2週間は見ておく方が安心できますから同じように2週間前までには手配をしておきましょう。
法要の後には会食を行いますし、香典返しの引き出物を用意することも必要です。
当日に間に合うよう2週間前までに用意をしておくと安心できます。
お店によっては早割がある場合もあります。