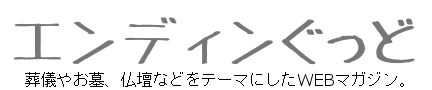霊柩車とは
霊柩車は亡くなった人を火葬場に送るための車だと思っている人が多いです。
昔は人力で御棺を自宅から火葬場まで運ぶ際に装飾をしていた輿(こし)を自動車で再現をしたものだといわれています。
自宅から主観をして運ぶのはかなり大変です。
そこで自宅から出棺して火葬場に運ぶために霊柩車を使っています。
ただ、最近では自宅で葬儀をすることは少ないです。
セレモニーホールを利用したり斎場を利用したりする人も増えています。
そういった施設の中には火葬場が隣接しているケースも多く、その場合には霊柩車を使用することなく火葬場まで御棺を運ぶことができるので霊柩車を使用しません。
霊柩車を使うには
道路運送法によって遺体は貨物として扱われます。
そのため国土交通大臣と地域運輸局長から許可を得ていないと運ぶことができません。
具体的には一般貨物自動車運送事業(霊柩限定)としての許可を受けた事業者が選任した一種免許を所持する運転者しか霊柩車を運転することはできないとされています。
そのため、誰でも運転できるわけではありません。
葬儀会社の中には二種免許を持っていないと霊柩車の運転ができないというところもあります。
ただ、霊柩車自体は一種免許で運転ができるので普通免許で対応可能です。
二種免許が必要となるのはバス型霊柩車のように遺族も一緒に乗せて運ぶタイプの霊柩車の運転で必要になります。
遺族を乗せての運転となると旅客運送となってしまうのです。
そのため二種免許も必要になっています。
実は霊柩車の数は市区町村といった自治体によって保有台数の上限が決まっているため、葬儀社がいくつでも好きに保有することができるわけではありません。
自治体に霊柩車の空き枠がないと保有することができないですし、葬儀社によって保有台数の割り当てもあるのです。
霊柩車には種類がある
霊柩車はもともとは輿を再現したものでした。
そのため宮型霊柩車と呼ばれているタイプが一般的です。
古くから利用されてきたもので多くの人になじみがあります。
ただ、最近では目立ちすぎるということで敬遠する人も増えていますし、施設によっては乗り入れ拒否をされることもあるのです。
そこで、数は減りつつあります。
装飾がされていない洋型霊柩車は近年数が増えているタイプのものです。
国産の大型車や大型の外車を利用して作ら得るもので御棺を簡単に淹れられるよう工夫もされています。
マイクロバスを改造したバス型霊柩車は一度に多くの人を運ぶことができるのが特徴です。
火葬場の駐車スペースが少ない場合や大人数での移動に便利として使われています。
最近では密葬や家族葬のような参列者が少ない葬儀で利用されることも多いです。