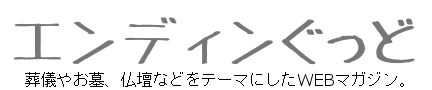仏壇の置き場所と方角は決まりがある
仏壇を購入する際にはどこに置くかということをきちんと考えることが必要です。
仏壇は向きが宗派によって決まっていますし、きちんと設置する向きに理由があります。
その宗派ごとに設置する向きがある理由を知ると供養にもつながるものです。
そこで、仏壇を購入する前にきちんと自分の宗派はどういった仏壇の置き方をするのか、ということを確認しておきましょう。
購入後に置けないとなることが避けられます。
仏壇の向きとその意味
宗教によって仏壇を置く方向が変わるのには宗教の歴史にかかわりがあります。
仏教ではあらゆる方角に仏がいるという考え方をするため、仏壇を置く向きには吉方位や凶方位が特にないのですが、北は避けることが一般的です。
東向きに仏壇を置く東面西座説というのはインドの慣習から来ています。
東は日の出の方角で立身出世の象徴でもあります。
そのため、インドでは主人は東向きに座ることが良いとされており、仏壇も東向きに置くのです。
また、極楽浄土は西方浄土とも呼ばれます。
これは極楽浄土が西にあるとされており、西を向いて祈ることから仏壇が東向きでもあるのです。
南向きに仏壇を置く南面北座説というのは中国の慣習からきています。
王をはじめとした高貴な人は南を向いて座る習慣があり、家来は北を向いて座るので、声に倣って敬う人は南向きに座るため仏壇も南を向くのです。
宗派による仏壇の向き
曹洞宗や臨済宗では仏壇は南向きに置かれます。
これは中国の習慣だけでなく、お釈迦様が説法をする際に南向きに座っていたことが理由です。
曹洞宗では場所条件があえば南向きに置くことを推奨しています。
浄土真宗や浄土宗、天台宗では、仏壇を東向きに置くことが一般的です。
この3つの宗派は本尊に阿弥陀如来を祀っており、西方浄土にいるとされています。
その方角に向かって祈るために仏壇は東向きなのです。
真言宗は本山中心説というほかの宗派とは違った形をとっています。
本山中心説というのは、名前の通り拝む方向の延長線上に総本山が来るように仏壇を設置する方法です。
そのため、自宅と総本山の位置との関係によって仏壇を置く方角は変わってきます。
また、日蓮宗は方角を全く気にせず仏壇を置くことになっており、方角も自由です。
ただ、あまりにも自由と聞くとほかの宗派と違うためにどういった場所に置けばいいか不安になることもあります。
そういった場合には吉方位を見てもらい置く方角を決めるのも一つの方法です。
仏壇を置く場所の注意点
仏壇の置き場所を決めるにあたっては、宗派ごとの方角以外にも直射日光や湿度にも注意をする必要があります。
直射日光や湿度によって仏壇が傷んでしまう可能性があるためです。
また、神棚と向かい合わせにすることは失礼になるとされているので設置場所に注意をしましょう。
ほかにも床の間についても仏壇を置くことは良いですが、床の間に向かい合うようにするのは失礼になりますから設置場所を考える必要があります。